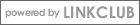20 July
僕らと宇宙人
1.
「宇宙人とコンタクトを取れる図形」と彼に説明されたが、
僕にはただの落書きにしか見えない。
1時間程掛かって、漸くそれが出来上がった。
グラウンドいっぱいに書かれたのは、不思議な模様だ。
「本当に来るの?」
不満げに石灰を撒く僕を見て、彼はにっこりと笑った。
「当たり前だろう。本に書いてあった」
その顔は真っ白だ。ホラー映画のメイクのようで可笑しい。
彼が爪先で引いた線を目印に、大きな袋から少しずつ石灰を撒く。
結構な重労働で、どうにも上手くいかない。
僕は額に流れる汗を両手で拭う。
徐々に気温が上がってきた。
早朝から始めたのに、太陽はもうすっかり姿を見せている。
「実はまだ、これで宇宙人と出会えた人は居ないんだ。」
彼はバスタオルで顔を拭いながらそう言った。白いのは取れていない。
「それは何処からの情報?」
「本に書いてあった」
彼ともう少しつき合いが長ければ、お前は本に書いてあれば何でも信じるのか、と責めたところだ。
「だから俺が目撃者1号だ」
「でも、誰も会ってないんじゃ、この方法で来るかどうかもわからないんじゃないの?」
「来るに決まってる」
謎の同級生は、ぎらぎらと目を光らせながらグラウンドを見ている。
こうしていればUFOが来ると、きっと本には書いてあったのだろう。
2.
「宇宙人の目撃者第2号にならないか。」
正面からそう声を掛けられても、僕に言われたものだとわからなかった。
「おい、待てよ。何処行くんだ」
脇を擦り抜けようとした僕を、彼は慌てて呼び止めた。
「僕?」
他に誰が居るんだ、という顔をされた。昼休みの購買だ。
「嫌そうだなあ。宇宙人は嫌いか?」
「別に、そういうわけじゃないけど」
この人は何者だろう、興味は少しそそられたけれど、
危ない人に絡まれた、と苦笑いをするしかない。
「じゃあ決まり。明日の4時、グラウンド集合。ちゃんと来いよ」
彼はそれだけ言うと、踵を返して去って行った。
「待ってよ! 4時って、夕方の4時だよね?」
慌てて言葉を返したけれど、無駄な質問だったと、すぐに悟った。
だから僕は、夏休み最初の日、
朝の4時から、学校のグラウンドで石灰と格闘している。
夏の陽は、朝からでもじりじりと皮膚を焼いて行く。
宇宙人は来ない。
その、当たり前の現実から逃げ出すように、僕は立ち上がった。
「ちょっと、ジュース買ってくるよ」
無駄な時間を使った。
スポーツドリンクを2本買って戻ろうとすると、
彼が僕を呼ぶ声がした。
小走りにグラウンドへ戻って、その光景を見た途端、
僕は苦笑いをするしかなかった。
彼の横に先生が立っている。
僕の姿を見つけると、こっちへ来いと、手招きしている。
僕の口の中は、砂のように干上がり始めた。
3.
宇宙人だなんて、馬鹿な話ですよね。
先生は、僕たちの話を聞いている間中ずっと険しい顔だった。
炎天下の立ち話なんて、早く終わらせたかった。
僕も、彼も、先生も汗だくだ。
「おい、宇宙人だよ!」
僕たちの横から、声がした。
僕は彼と顔を見合わせて、声の方へ振り返った。
野球部のユニフォーム姿の生徒が、目を丸くして立っていた。
振り返った僕たちの顔を見ると、野球部は腹を抱えて笑い始めた。
清々しい程の爆笑だ。
「お前、顔が灰色だぜ。ソックリだよ、あの頭のでかい宇宙人に!」
確かに、僕たちは薄汚れた石灰が顔中に溶けて広がっていた。
偉そうな相棒は、目だけがギラギラと光って、本当に宇宙人みたいだ。
可笑しくなって、僕は吹き出した。
「ふん!お前は目撃者2号だからな」
彼はそう言って、どこまでも偉そうに、僕を指差した。
4.
「宇宙人とコンタクトを取れる図形」だなんて、
いったい彼は、どんな本を読んだんだろう。
汗と石灰にまみれて、炎天下で先生に説教をされて、
夏休みの最初の朝は、とんだ始まりだった。
「じゃあな」
道の途中で、僕たちは笑い合って別れた。
次に彼と会うのは、きっと夏休みが明けてからだろう。
ぼんやりと見上げた夏の空は、狭くて近かった。
青を取り囲むように、白い雲がそびえている。
きっと今日は、もっと暑くなるんだろう。
その時、
厚い入道雲の中から何かが飛び出した。
ハッとして振り返ると、
彼と別れたばかりの道に、人影はなかった。
彼を呼ぼうとしたけれど、口から声が出ない。
そういえば、僕は彼の名前すら知らなかった。
もしかしたら、
宇宙人目撃者の第1号は、僕だったのかも知れない。
script / 木村 静花
30 March
はじまりの春
1
何故私はここに来てしまうのだろう。回り道だってあるというのに。
早朝の暗闇の中に、ぼんやりと見える上り階段。ここを上れば学校まで程せずに着くが、暗い間は通りたくない。
左手に墓、右手に公園が望める。どうしても、私の想像力を不本意な方に掻き立てるのだ。
下から見える限りでは墓も公園も見えないのだが、突然開けてそれが現れる。
その不意打ちも、また嫌だった。
空は徐々に明るさを帯び始め、階段の上では街灯の灯が消えた。
私は、石段を1歩踏み出した。
きちんと段数を把握しているわけではないが、30段程の苔むした階段である。
少し上れば、墓と公園が見えてくる。
公園は中々の広さで、見下ろすような桜が数本、並んで咲いている。管理はされていないのか、雑草が生い茂っている。
遊具といってもブランコと鉄棒が取り残されたようにあるだけだ。子供が遊んでいるのも見ない。
遊具や墓が目の前にあることもあるだろうが、1番はこれだろうと考えている。
立ち並ぶ満開の桜に混じって、黒い大きな桜がある。魔女が手を振り上げてるような様だ。
黒い――というのは火によって焦げてしまったもので、木が死んでしまっているのかはわからないが、花を付けた所は見たことがない。
ここには、以前家が建っていたらしい。
不注意から火が起きて全焼し、沢山のものが燃えてしまった。
大きな桜と一緒に、大事な息子までもが犠牲になってしまった。
彼の家族は今、遠くで暮らしている。
しかし墓は、ここにあるのだそうだ。
黒い桜も、そこが家だった時には花を付け、家族の目を楽しませたことだろう。
今は蕾すら付けない。
私はいつものように階段を上っていた。
公園を通り過ぎて直ぐ。きい、と濁った高い金属音がした。背後でブランコが鳴ったのだ。
誰も居なかった筈だ。風だって、無風に近い。柄にもなく驚いて振り返る。
厚い雨雲を抱えた広い海が、静かに騒めいている。
2
風がけたたましく鳴っている。叫び声のように聞こえた。
昨夜から徐々に聞こえる勢力を強めている嵐は、のしかかるように重たい。
「こんな風じゃ歩けもしないんじゃない?」
質問ともわからないことを、母は言った。
「それなのに父さん大丈夫なの?」
「平気だって」
母は欠伸をしながら台所に消えた。もう夕飯時か。
庭に出る窓から外が見える。植木鉢などは全て片付けられている。
風に揺らされた木を見ていると、もう風向きなんてものもわからない。
隅の方で、小さな子供の影が動いた。
まさか、と立ち上がり窓に駆け寄るが、もうその姿は見えない。
窓に手を掛けると、凄い圧力がかかっている。両手で横にずらし、取り残されたサンダルを引っ掛けた。
温かな風は本性を現したのか、切り裂くような速さで私向かってくる。雨はそこまで強くないが、痛い。
風が目に見える筈がないのに、その動きが見て取れるようだ。
まるで直感的に、私は外に飛び出した。
あの影が誰だか――何なのかも、わからないのに。
低い風の音の中に、例の金属音が聞こえる。
――ブランコだ。
ふと顔を上げると、あの階段が伸びていた。
風の合間に、ブランコが揺れる音がする。規則的な高音。
誰かが漕がなければ、あんな音にはならないだろう。
しかしこの嵐の中で、あの軽やかな音を鳴らすのは無理だ。
さっきから、非現実的な話が、自分でも不思議な程にしっくりとくる。
横殴りの風に急かされて、1歩を踏み出した。
雨なども気にならなくなり、首を持ち上げる。
黒い桜の木の頭が、屋根の上から見え始めた頃だった。
「何してるんだ」
横から掛けられた声に、私は肩を跳ねさせた。
雨で黒ずんだスーツを着た父が立っていた。手に持っている傘はひっくり返っている。
我に帰ってみれば、確かに何をしていたのだろうと思った。
「そっちこそ」
私は声を張り上げる。
「子供を見た気がしたんだ」
父は真剣な顔で言った。顔に出すことはなかったが、私は驚いていた。
「私も、見た」
それだけ言って、振り返って階段を下った。
ざわざわと花びらが散り、みるみると視界を埋め尽くしていく。
ブランコの音はいつしか止んでいた。
3
さんさんと日の降り注ぐ、嵐の後の晴天。
そよぐ風は温かく、耳元で髪を揺らしている。からりと晴れた空を仰ぐと、小さな白い雲がぼっかりと浮かんでいた。
水溜まりにはふらふらと散らされた桜の花びらが浮かび、あの階段には桃色の絨毯が敷かれた。
誰に踏まれた跡もなく、水を受けて新雪のようにきらきらと輝いている。
3月の終わりの日。昨日までは色付いていたそれが、気休め程度の花びらを残して光っている。まだ風に任せて散っているのもある。
階段から、肌の白い女性が下りてきた。淡い色のワンピースを風に揺らし、穏やかな顔付きの中に多少の影を覗かせている。
頬から首にかけて、火傷の痕が見えた。
口元に微かに浮かんだ笑みを、私は見逃さなかった。
墓石にも公園にも、散った桜の花びらは、場所を選ばずに見える。
ブランコは清々しい風の中で小さく揺れている。
立ち並ぶ桜の木。それに混じった1本の黒。
私はその光景に息を飲んだ。
大きく広げられた枝には、満開の桜の花が付いている。
昨夜までは影のように黙っていた黒い枝が、さわさわと鳴っているのだ。脆く崩れてしまいそうに見えた幹も、生命力を溢れさせている。
桜吹雪と共に、墓地から線香の煙が流れてきた。
彼が喜んでいるのだろうか。
子供たちが階段を下りてきて、笑いながら公園に飛び込む。ブランコに飛び乗った子は、高らかな音を鳴らしながら空へ舞い上がる。
もうそこには、淋しさも恐怖もない。
喝采のような強い春風が、花びらの香りと一緒に何処かに飛ばしていってしまったようだ。
script / 木村 静花